〇 12月定例会
令和6年の県議会12月定例会は12月2日に開会し、同20日に閉会しました。人事委員会の勧告に基づき県職員給与や特別職の報酬を引き上げる給与条例改正案や86億2千万円を追加する一般会計補正予算案など計42議案を原案通り可決しました。
特に菊川市に関係する議案として「特定都市河川浸水被害対策法施行条例」及び「静岡県核燃料税条例」が上程されました。内容は後述します。所属する危機管理・くらし環境委員会では次の意見を述べさせていただきました。
〇 広域避難計画の策定状況について
浜岡原子力発電所から31キロメートルを目安に原子力災害対策重点区域が設定されています。この 区域には11市町が含まれ、それぞれの市町は、災害対策基本法及び市町の防災計画に基づき、浜岡原子力発電所を原因とする原子力災害に備え、原子力災害発生時に市民が放射線防護対策を実施し、必要な時には一時移転または避難が実施できるよう、あらかじめ避難等の方法や避難先等について定めた広域避難計画を策定しています。
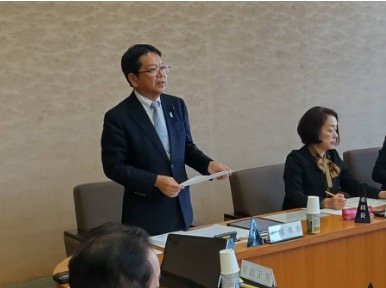
原子力災害が単独で発生した場合等に備え、まずは静岡県内市町、加えて隣接県や東海地方の県に避難先を確保することになっており、大規模地震との複合災害時などに備えては関東甲信地方や北陸地方の都県に避難先を確保することになっています。菊川市は、単独災害時は浜松市、湖西市、愛知県豊橋市及び田原市に、複合災害時は富山県高岡市、氷見市、砺波市及び小矢部市に避難することになっています。ところが、未だに避難先での避難経由所が決まっていなかったり、避難経由所の施設管理者の了解が得られていない市町もあります。
また、県は、「静岡県地域防災計画 原子力災害対策編」において、原子力災害対策重点区域の病院及び有床診療所、並びに入所型の社会福祉施設では、入院患者や入所者の避難手段に配慮した避難計画を定めるものと規定しています。避難計画策定の対象となる病院は57施設、社会福祉施設(入所)は349施設あるにも関わらず、避難計画の策定が済んでいる病院はわずか1施設、社会福祉施設(入所)は51施設に過ぎません。
現在、浜岡原子力発電所は運転を停止していますが、今でも9,000千体に近い使用済及び使用途中の燃料が保管されており、避難経由所の決定、病院等及び社会福祉施設の避難計画は早急に策定すべきであり、県がしっかりと指導するように強く求めました。
〇 災害時借上げ住宅の柔軟な対応
災害によって住宅が全焼・全壊または流出して居住するところがなく、自らの資力をもって住宅を確保できない方に対して、仮設住宅建設のほか、県が民間の賃貸住宅を借り上げて入居してもらう「災害時借上げ型応急住宅」という制度があります。これは災害救助法に基づいて運用されているものですが、運用細則例において「原則として昭和56年以降に建設され、被災後に使用が可能であると確認された住宅」と定められています。
令和3年の熱海市の土石流災害のときには、すぐにでも入居が可能な住宅があるにも関わらず昭和56年5月以前の旧耐震の建物であったため、入居できなかった例もありました。運用細則例では「原則として昭和56年以降に建設され」と定められており、例外的に認められるケースがあるはずです。どういう場合に認められるのか、県は内閣府と協議して、県民に寄り添った対応をしていただきたいと申し入れました。
〇 黒沢川を特定都市河川に指定
国は令和7年4月に一級河川黒沢川を特定都市河川に指定するよう準備を進めています。一級河川は国が指定するため、県は法律で定められた必要事項を定めるために条例を制定しなければなりません。静岡市及び浜松市の両指定都市を除いて、黒沢川が県下で初めて特定都市河川の指定を受けるため条例の制定が必要になったものです。
【特定都市河川】
特定都市河川の指定は、特定都市河川浸水被害対策法に基づいて行われるもので、同法は都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川流域における浸水被害対策の新たなスキームとして設定されたものです。
特定都市河川に指定されると流域水害対策計画を策定し、この計画に基づいてハード対策(例えば遊水地の整備や河道掘削等)が行われます。現在、市は流域の岳洋中学校の校庭を利用した校庭貯留施設を整備中で、今後田んぼを利用した遊水地の整備にも取り掛かります。こうした取組に国や県の支援を受けることができるようになります。
〇 核燃料税の延長
令和2年4月1日に施行した静岡県核燃料税条例の有効期限が令和7年3月31日に到来することから、引き続き核燃料税の賦課徴収により原子力発電所の立地に伴う周辺地域の財政需要に対応するため、条例を制定したものです。
課税客体は、発電用原子炉への核燃料の挿入(価額割)及び発電用原子炉を設置して行う発電事業(出力割)であり、運転が停止していても価額割は課税されます。令和5年度の税額はおよそ12億円で、そのうちの2割が原子力災害対策重点区域の11市町の交付され、8割は県が直接使用しています。菊川市にはおよそ1,500万円ほどが交付され、道路整備などに使われています。
〇 耐震診断助成を1年延長
県では、木造住宅耐震化プロジェクト「TOUKAI-0(トウカイゼロ)」に取り組んでいますが、耐震診断助成が令和6年度で、耐震補強助成等が令和7年度で期限を迎えます。しかし、能登半島地震の発生や南海トラフ地震臨時情報の発出に伴い、令和6年度は耐震診断助成の申請が当初の予想を大幅に上回ったことから耐震診断助成を1年間延長する方向で考えています。
令和8年度以降の耐震補強助成については、高齢化率の高い地域で耐震化率が低い傾向が見られることから、耐震補強のみならず、高齢者が取り組みやすい対策の拡充など、市町と連携して検討していきます。
〇 緊急安心電話相談窓口 #7119 24時間体制に
県消防保安課は、令和6年10月1日から、おおむね15歳以上を対象とした救急安心電話窓口「#7119」(シャープなないちいちきゅう)を設置し、病院に行った方がいいのか、救急車を呼んだ方がいいのか迷ったときの電話相談に応じています。
現在は、平日の18時~翌8時、土曜日の13時~翌8時、日曜・祝日の終日、に限られていますが、令和7年4月1日からすべての曜日において24時間体制で相談に応じることとなります。
